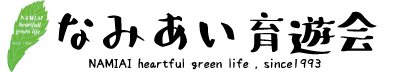コラム(中日新聞・達人に訊け!掲載記事②)山村留学というもの
さて、今日は私たちが事業として大切にしている、山村留学について書いてみます。自然の中での子どもの成長や子育ての様子は、すみません、今回はちっとも触れません。まずは山村留学というものを知っていただきたいからです。
山村留学は長野県が発祥の地です。東京都で先生をされていた方が当時の八坂村(現大町市)でスタートされました。昭和51(1976)年のことです。
山村留学とは、ざっくり言って、1年間小学生あるいは中学生が都会の家を離れ、自然豊かな山村の里親さんのもとで生活をする、あるいは寮で集団生活をする、というものです。

山村留学が生まれたころの日本は、目覚ましい経済成長を遂げようとしている時期でした。しかしその陰で、都市への人口集中と周辺部の過疎化の問題も同時に生まれていたのです。国もそのことを重視し、昭和45(1970)年には、「過疎地域対策緊急措置法」という法律を制定しています。・・・今に続く問題ですね。難しい問題で、まるで解決されていません。
当時、都市では公害(これは今よりもかなり酷かった)やコミュニティの希薄化が可視化し、周辺部では人口減少と活力の低下が問題となります。しかし経済成長の波には乗りたいですから、人々は都市への人口集中を本気でやめてしまおうとはなかなか思いません。そこで、都市と山村(周辺部)の交流、という考え方になります。都会で暮らしたいけれど、生活の一部や人生の一部は周辺部にあってもいいよなあ、という考えには、多くの人が頷けるでしょう。山村留学誕生の背景には、そういうこともあったのかなあと思います。


また、実際山村留学の事業に携わって思うんですが、山村という環境が大きな教育資源、ということは令和の今でもその通りと思っています。自然が身近にあり、人間以外の生き物がふつうに生きていて、人が自然の一部なんだということを感じさせてくれますし、コミュニティがちゃんと残っていて、人は人の中で生きるんだということを、くらしをもって学ばせてくれます。
山村留学という事業の誕生は、本当に先見の明により生み出されたものなんだなあと感心します。


その後40年以上が経過しました。幾度もピンチはあったと思います。たとえば、平成の大合併(山村留学のメイン舞台である小さな村がなくなる)。たとえば令和のコロナ(都市との行き来ができなくなる)。それぞれでだいぶ揺れたこの業界ですが、理念とアイデアと実行力、それから情熱を持って事業に取り組んでこられたところは、その後もきっちり山村留学を続けていらっしゃるようです。私たちも正直、ほんとにがんばりました。
そんな山村留学ですが、山村留学いい、いい、と言っても、実際参加してもらい、その上で、確かにいい、と思っていただけないとホントの魅力にはなりませんよね。次回は、こういうところが魅力だと思うんです、ってところに触れていきますね。